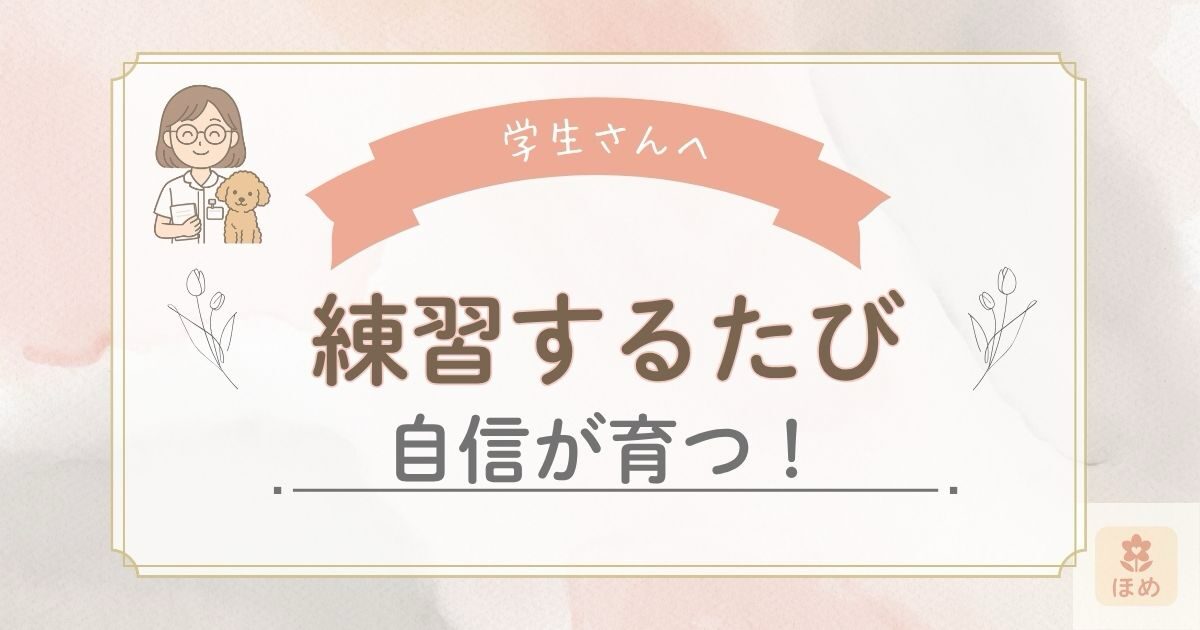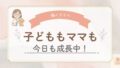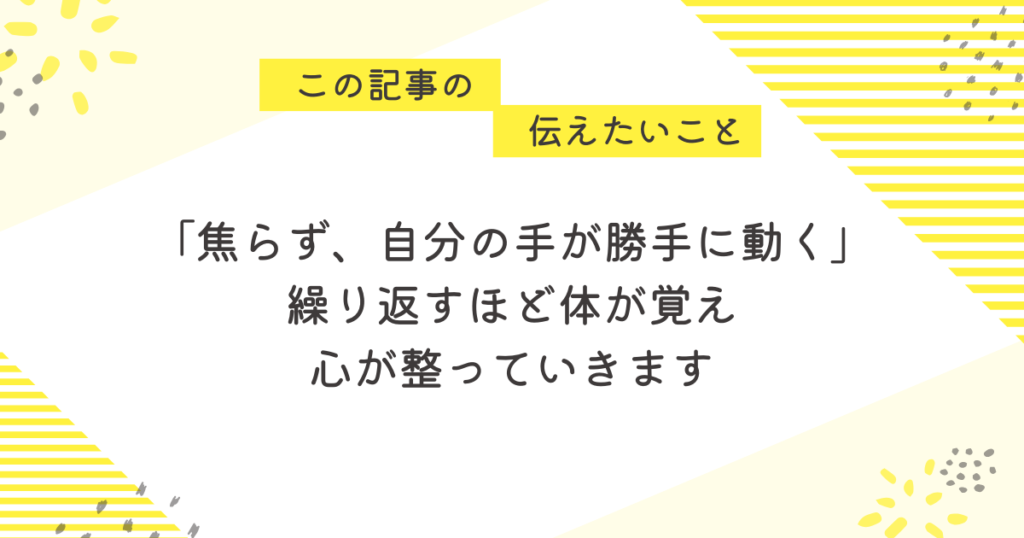
結論:その緊張は、あなたが真剣に取り組んでいる証です。一日ひとつ手技を覚えたら、1年で360個のスキル。繰り返すことで言葉も手技も自然に出てくる。
はじめに
こんにちは、miuです。
看護学生さん、助産師学生さん、看護ケア・助産ケアの実技の授業はもう始まりましたか?
この時期、多くの学生さんが「技術チェックが怖い」「緊張してうまくできない」と感じているかもしれません。
初めて触れる手技、慣れないし、名前もわからない器具、先生に見られている緊張感…。
それに加えて「できて当然」と思われるような空気に、プレッシャーを感じている方もいるのではないでしょうか?
今日はそんなあなたに向けて、私自身の体験を通じたメッセージと、解決策をお届けします。
看護学生・助産師学生が思う実技テストの悩み
私も学生時代は、実技テスト自体の意味もよくわからず、困った思い出があります。よく覚えている実技のテストは、助産師学校での「新生児の出生時全身観察」でした。テスト自体は口頭で、観察部位、ポイントを発表していくスタイルでしたが、とても緊張したことを覚えています。チェックポイントは40項目ほどあり、覚えることも大変でしたし、それを口頭で先生に説明しながら実際の赤ちゃんの観察部位を示すものでした。どれだけ資料を見直し、友人と練習を重ねても、本番になると…頭が真っ白。手も声も震えてしまい、思ったようにできませんでした…。
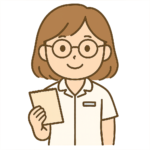
今振り返ると現場でそのまま生かせる、実用的なテストだと実感しますが、その時はとても難しく感じましたね。特に学生のうちは実践のイメージもつかず、ただ覚えなくてはという意識だったのかもしれませんね。
では、多くの看護学生、助産師学生が、直面する、実技テストに対する心理的状況、実技テストの悩みについて以下にまとめてました。私のように困った内容が多くありますね。

手技・技術そのものが不安…
- 正しい手順が覚えられない
- 自信をもって患者さんに実施できない
- 清潔操作(無菌操作)があやふやになる
- 赤ちゃんの抱き方、母乳の与え方、触れ方が怖い(助産)
- シミュレーター(人形)ではできても、実際の人では緊張してできない
- 「どこまで声をかけていいか」コミュニケーションがわからない

緊張・不安・プレッシャー…
- 見られていると手が震える
- 実技チェックが怖くて前に進めない
- 他の学生と比べて自分だけできていない気がする
- 指導者に声をかけるのが怖い・話しかけづらい
- ミスした後に切り替えられず落ち込む

学習方法の迷い…
- どこから勉強すればいいか分からない
- 時間が足りず、練習が不十分になりがち
- 頭では分かっても、体がついていかない
- グループでの練習がやりづらい(恥ずかしい、質問しづらい)
- 練習の相手によって緊張感や雰囲気が変わる
たくさんの、悩みがあがっていますが、皆さんも当てはまる部分はあったでしょうか?
実技の学びは、現場に一番近い科目
皆さんも感じている通り、実技の授業は、実際の業務と直結している一番実用的な科目です。
- なぜこの手技を行うのか(目的)
- どんな効果があるのか
- その結果、患者さんにどんな変化があるのか
- 今後の経過にどう影響するのか
これらを理解し、実際に手を動かしながら身につけるのが実技の授業です。私はこの考え方が欠けていたのだと思います。皆さんはこの実技の演習、テストが、そのまま現場で実行するもの、という意識をしっかり持って学んでいただけると現場のイメージもつきやすいと思います。
実習や現場に行く前に読んでおきたいヒントについての記事は他の記事でも紹介しています。ぜひそちらも参考にしてください。→不安な看護学生さんへ|実習前に知っておきたい3つの心構えと準備
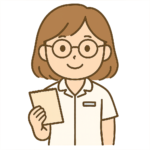
実技は、患者さんや妊産婦さんの命や健康を守る技術です。手順を守り、安全に配慮した行動が求められます。清潔操作や感染予防など、ミスが命取りにならないための基礎、なぜその手技を行うのか、どういう目的があるのかを理解した上で動けるようにすることが大切です。ただ“手順通りにやる”ではなく、考えて動きましょう。事前に練習しておくことで、実習や現場でも焦らず動けるようになり、自信があると、患者さんや家族にも安心感を与えられます。これらの意識を持って、実践のイメージを持って臨みましょう。
看護技術教育における反復練習と成長実感
さて、皆さんの実技テストへの悩みを解決する方法は、何が必要なのでしょうか?以下に看護技術教育における反復練習についての資料を紹介します。
防衛医科大学校の資料によると、
“身体で覚えるまで繰り返し練習することが大切。
その中で、成長の発見ができる工夫を取り入れると良い。”
と明記されています。具体的には、どういう意味なのでしょうか?
- 「身体で覚える」ための反復練習
- 単なる口頭説明や映像視聴では不十分。身体が自然に動くレベルまで、何度も手を動かす練習が重要です。
- ただ反復するだけではモチベーションが下がる
- 単調な練習が続くと“練習疲れ”が起きるため、心理的に続けにくくなることも。
- スタンプラリー方式で「成長」を実感できる工夫
- 技術試験をクリアするごとにスタンプやサインを集めていく方式。
- 目に見える結果=達成感が刺激となり、さらに練習を続ける源になります。
引用:防衛医科大学校:「看護技術のコーチング〜心躍る創造〜」pdf
まずは体で覚えることが大切、しかし単調な練習ではモチベーションが下がるため、スタンプラリー方式での目にみえる達成を作ることがモチベーションをキープするためにも重要とのことです。
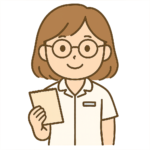
この内容は、実技の内容を身につける上で、とても重要なことですね。要は反復練習が重要ということです、繰り返し行うことで体で覚えることが必要なのですね!小さな達成感の積み重ねで続けられる、持続力も大切ですね。
では反復練習と通じて、どのように技術習得につながるのでしょうか?以下の資料も参照してください。
スポーツコーチング理論では、反復練習を通じて動作を修正・洗練し、自動化へと導くプロセスが、技術習得に不可欠とされています。これは看護技術の習得にも当てはめられる重要な考え方です。
反復練習の価値とは?
1. 伝統的(ブロック)練習による自動化
- 情報処理モデル(Fitts & Posnerの「認知→連合→自動化」モデル)では、同一フォームを繰り返すことで身体が反応を自動化し、手技が無意識レベルで行えるようになるとされます 。
2. 「反復なき反復(Variability)」による柔軟性
- 同じ動作を繰り返すだけでなく、微妙に条件を変えながら練習することで、環境の変化に適応できる柔軟な技術が身につくとするモデルもあります(Bernsteinの「反復なき反復」) 。
3. 制約主導アプローチ(CLA)
- 環境・課題・個人の特徴を変えながら練習することで、実践的かつ状況に応じて使えるスキルが形成されると説明されています 。
4. 故意的反復(Deliberate Practice)の重要性
- Ericssonらの研究によれば、ただ繰り返すだけでなく、“意図をもって改善点を絞り・難度を上げながら”練習することが、熟練度向上に効果的とされています 。
看護技術への応用
スポーツで使われるこれらの練習手法は、看護・助産の技術教育にもそのまま応用可能です:
- ブロック練習:手順を完全暗記し、自動化するために反復
- 状況変化練習:練習環境・患者役・時間制限などを変えながら実践力を強化
- 故意的反復:単なる反復ではなく、振り返り・フィードバックを織り交ぜて改善する
これらを看護教育に取り入れると、
– 単なる繰り返しではなく、
– 状況を意図して変化させながら、
– 毎回「何を改善したか」を記録しながら練習することで、
「本当に使える技術」「判断できる力」が自然とついてくるようになります
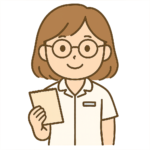
スポーツの原理が看護技術につながるとはイメージがつかなかったですね。でも、自分の実技手技が、自動化してできるようになれば、テストにも安心して臨めそうな気がしてきますね!以前の私の失敗は自分の知識がうろ覚えのまま挑んでいたのだと思います。単純に勉強不足、練習不足でした。繰り返すことで、知識も繰り返し身につくことができ、言葉も手技も自然に出てくるようになっていくのですね。「体で覚える」って、本当に大事ですね。
繰り返し練習による緊張緩和の効果
実技の学習は、とにかく繰り返して練習をしていくことが必要ということがわかりましたね。
では、学生さんのもうひとつのな悩みの緊張感についてはどうでしょうか?見られていると緊張してしまう、テストを受ける場面では緊張して通常の能力が発揮できない、焦って落ち着こうとすればするほど緊張が増して調整が難しくなる…いわゆる「あがり」について、以下に参考資料をまとめてみました。繰り返し練習とつながることはあるのでしょうか?
繰り返し練習と緊張緩和
- 心身の過緊張の調整に有効なカウンセリング技法では自律訓練法やマインドフルネスなど、繰り返し行うセルフ訓練が緊張や不安のコントロール、緊張や不安を和らげ、心を整えるために効果的である紹介されています。
つまり、同じ行動を何度も繰り返す=体が慣れてくることで、心も安心を覚えるという仕組みがあるのです。 - 参考:[心身の過緊張の調整に有効なカウンセリング技法(J‑Stage)]
- 本番の恐怖と緊張を乗り越える8つの方法では音楽や演奏の本番に向けて「繰り返し練習やルーティーンが緊張緩和に役立つ」として具体的に紹介されています 。例えば、同じ場所で、同じ手順で、同じように声をかけながら 何度も練習することで、それが本番でも「安心の流れ」として再現されやすくなるのです。
- 参考: [本番の恐怖と緊張を乗り越える8つの方法(バジル・クリッツアー音楽ブログ)]
本番に強くなるために、練習で「安心の型」をつくろう
繰り返し練習は、ただ技術を覚えるためだけではなく、心の準備にもつながっています。
「焦らず、自分の手が勝手に動く」そんな状態は、反復の積み重ねから生まれます。ぜひ、「安心できる練習」を少しずつ増やしていきましょう。繰り返すほど、体が覚え、心が整っていきます。
まとめ
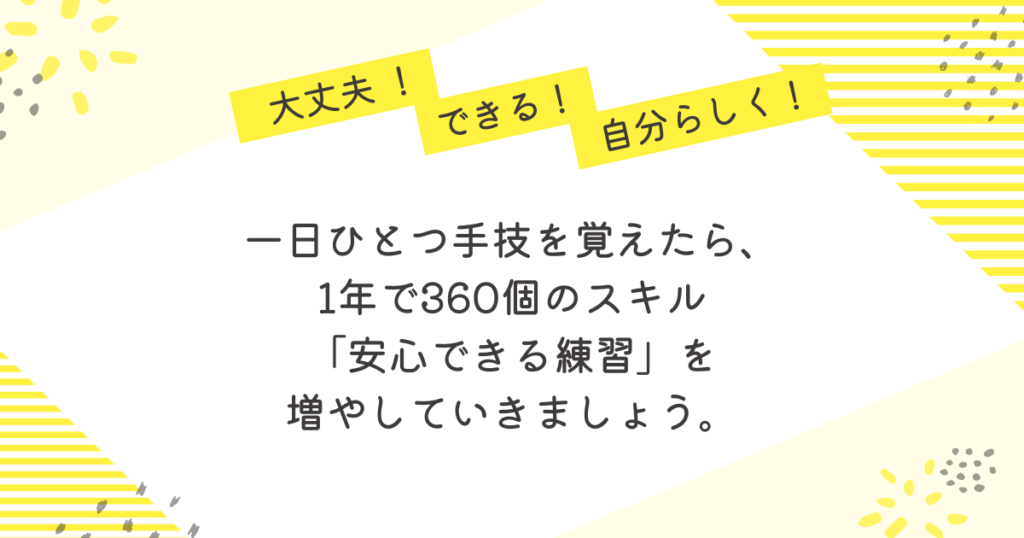
では今日のまとめです。
- 看護学生・助産師学生が思う実技テストの悩み
- 実技の学びは、現場に一番近い科目
- 看護技術教育における反復練習と成長実感
- 繰り返し練習による緊張緩和の効果
皆さん、今日の記事はいかがだったでしょうか?看護技術、助産技術に関しては、実際に手を動かして自分のものにしていかなくてはいけません。
「やるしかないのかな?」と思っていても、なんとなくでやっていませんでしたか?(私が学生の頃そうでした。)でも、繰り返す練習で手技が自動化すること、繰り返す練習で、心が安定すること、科学的に証明されてるとわかると、練習に臨む姿勢も変わってくるのではないでしょうか?緊張することもあると思いますが、極力その緊張が減らせるように、自分が納得できるように練習してみてくださいね!
一日ひとつ手技を覚えたら、1年で360個のスキル。
それは、もう誰にも真似できない、あなただけの宝物になります。
緊張しても、うまくできなくても、何度でも挑戦すれば大丈夫。「できない自分」を責めるより、「あきらめずに向き合った自分」をしっかり褒めてくださいね。
大丈夫、応援しています!
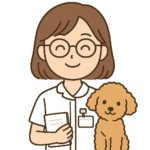
miu|助産師・2児の母・ブログ運営中
20年以上、病院で助産師として勤務。新人時代の不安や戸惑い、子育てと仕事の両立に悩みながらも、周りに支えられてここまできました。
このブログでは、助産師学生・看護学生、そして働くママたちが「今日もがんばったね」「ちゃんとやってるよ」と、自分を優しく認められるような言葉を届けています。
あなたがちょっとだけ元気になれる、そんな場所になりますように。