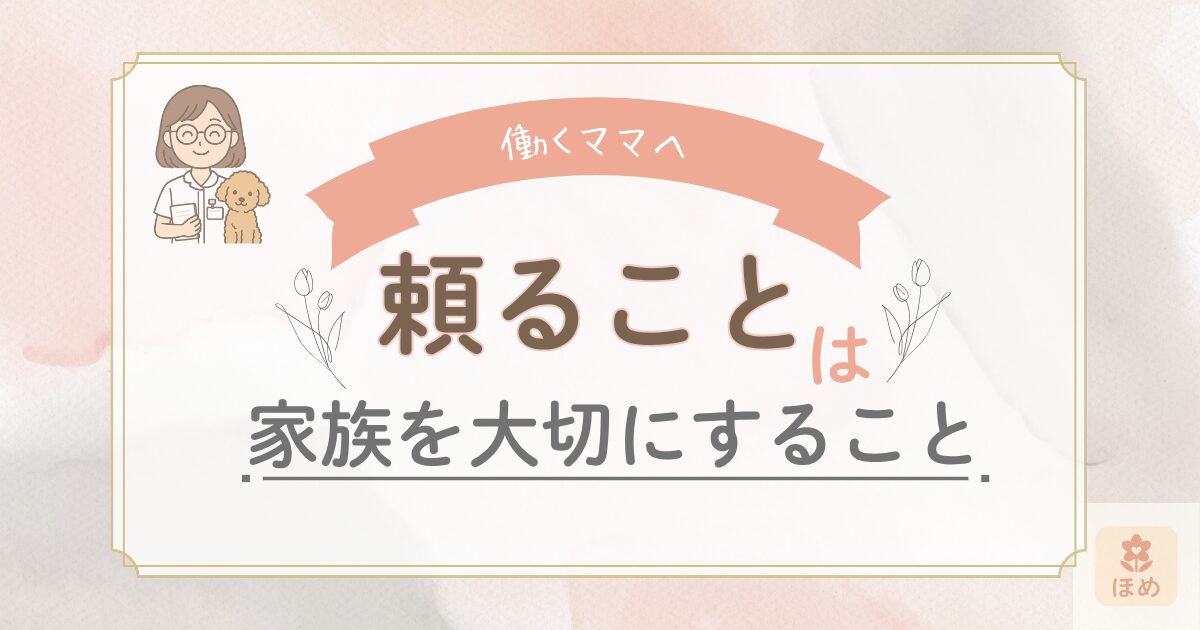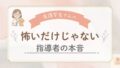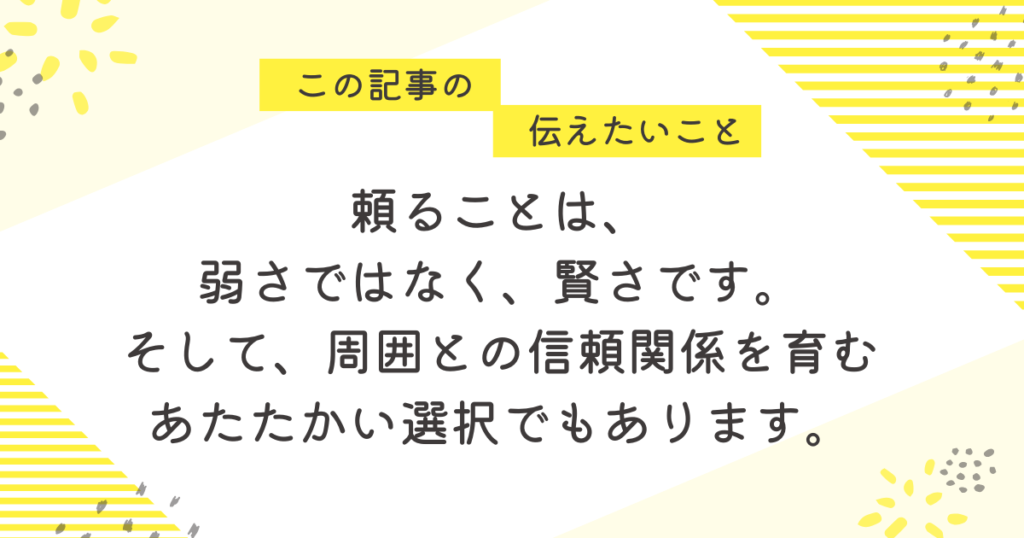
結論: 頼ることは、あなたが家族や自分を大切にしているからこそできる選択です。
はじめに
こんにちは。miuです。
このブログを読んでくださっているあなたは、看護師・助産師として働きながら、ママとしての毎日も全力で過ごしている方かもしれませんね。いつもお疲れ様です。
夜勤や早番、遅番のシフトは、保育園や学校のスケジュールが合わないことに悩んでいるママも多いと思います。送り迎えの調整、急な体調不良、子どもが泣いて「ママ行かないで」と言われた日のつらさ――そのすべてを、きっとあなただけでなく、多くの人が抱えながら頑張っています。
今日はそんなあなたに、私自身の経験をお話ししながら、「頼ること」への考え方や、働くママたちが実践している対策とそのメリット・デメリットをお伝えしたいと思います。
私の経験:復帰の喜びと、葛藤の両方を感じた日々
私自身も、2人の子育てを経験してきました。産休から復帰したときのことを今でもよく覚えています。
それまで育児に専念していた日々から、助産師として再び歩み出せることが本当に嬉しかったんです。
まずは大人と会話できることが嬉しかったのを覚えています。職場の同僚と育児の悩みを話しながら共感し合えたり、お昼休みにゆっくりと食事ができることが、心からありがたかったです。
大人と会話する時間が、悶々とした気持ちをスッと軽くしてくれる。仕事復帰によって「社会とのつながり」や「自分の時間」を感じられることは、思っていた以上に大きなメリットでした。
でもその一方で、夜勤や早番・遅番のシフトと、保育園の送迎時間とのバランスにはいつも頭を悩ませていました。急に仕事を早退しなくてはいけない時の心苦しさもありますね。
急な保育園の呼び出しに対しての気まずさ、心苦しさに対しての記事は他の記事でも紹介しています。
我が家の場合、夫は残業がほとんどない仕事だったので、日勤の日のお迎えはお願いできました。
けれど夜勤の前後だけはどうしてもカバーできず、祖父母の力を借りることが必要でした。
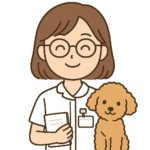
産休明けは特に、大人との会話自体にありがたみを感じました。食事は昼休みが1日の中で最もゆっくり食べられる時間でした。大変さもありますが、職場に助けてもらったことも多くありました。
義理の祖父母へのお願い…私が気をつけたこと
特に気を使ったのは、義理の祖父母へのお迎えのお願いでした。もちろん、状況の理解はしていただいていたと思います。
でも、「嫁」という立場から毎回お願いすることに、どこか申し訳なさを感じてしまい、「本当にいいのかな…」と気持ちが重くなることも正直ありました。それでも、どうしても自分だけでは回らないスケジュール。「迷惑をかけたくない」と思うあまり、心が苦しくなることもありました。
そんなとき、ふと視点を変えてみたんです。
「孫と触れ合える時間ができて、良かったって思ってもらえたらいいな」そう考えて、しっかり、堂々と甘えさせてもらうことにしました。実際にも、孫と触れ合える時間があって喜んでもらえました。
頼ることは弱さではない。むしろ、家族の関係を深める大切な手段でもある――
そうやって気持ちを切り替えたことで、私は少しずつ“乗り越える”というより、“受け入れて前に進む”ことができました。
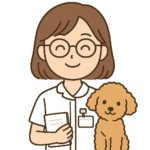
子供を預けるとき、夫の家族に頼む場合は、そのお宅のやり方にある程度お任せすることもあります。自分のやり方と違っても、よしとする考え方を持つと心が軽くなるでしょう。もし守ってほしいこと、注意事項があればあらかじめお願いして、おくと良いでしょう。
働くママが実践している対策と、そのメリット・デメリット
私の場合は、近くに頼れる家族がいましたが、そうでない方も多くいらっしゃると思います。
現在は家族、友人の援助のほか、さまざまなサービスもあります。自分に合った方法で対応されると良いでしょう。いくつか紹介をさせていただきます。
① 家族の協力(夫・祖父母)
メリット
・費用がかからず経済的(お礼の言葉を添えたり子供のお手紙も嬉しい!)
・信頼できる身内なので安心(愛情込めて子供を見てくれます)
・子どももなじみやすくリラックスできる(子どももじじばなら楽しく過ごせますね!)
デメリット
・祖父母の体調や仕事の都合に左右される(急なことに対応しにくい)
・頼むことに心理的な気遣いが必要、そのお礼をどうするか悩むこともある(お金渡したほうがいいの?お礼の品は何がいいの?かえってお金がかかるかも…)
・夫の仕事との調整が難しい場合もある(急な対応は仕事中はみんな難しい…)
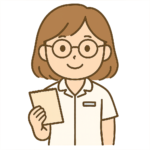
家族であってもお礼は必要ですね!”お金”のお礼はいづれ支払いが大変になることも…途中でやめることもできないこともあります。品物やお食事に誘うなどにして、しっかり言葉でお礼を伝えることも大切です。
② ファミリーサポート・ベビーシッター
市町村のそれぞれサービスもあると思います。ぜひ確認して、活用しましょう。丁寧に相談に乗ってくれます!民間のベビーシッターサービスも、プロの方も多くいらっしゃいますよ!
メリット
・早朝や夜間など柔軟に対応してもらえる(柔軟な対応が本当にありがたい)
・専門のサポーターなので安心(保健師、助産師、保育士など専門職の方もいます)
・保育園との橋渡しも可能な場合あり(迎えから行ってもらえるサービスも確認してみましょう)
デメリット
・費用がかかる。時間500〜3000円など。(平日や夜間などで料金変動も大きくなることも)
・毎回同じ人に頼めるとは限らない(その人によって合う合わないあることも)
・事前の登録や相性確認が必要な場合も、突発的な対応には向かないこともある(急な対応には向かない)
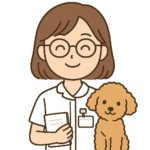
市町村のサービスもあり、料金も安くできることも。民間のサービスも合う方に出会えると、長く対応させてもらえることもあります。自宅の近くや職場の近くで探してみましょう。
③ 夜勤・遅番免除/時短勤務制度
職場での先輩や同僚はどうされているか、一歩先ゆく方のお話を聞いてみましょう。そして職場ごとにどんな内容の使える制度があるのか確認すると良いでしょう。職場としては早めに申し出をしてくれると、調整がしやすくありがたいこともあります。
メリット
・生活リズムが安定しやすい(時間が固定されているため、子供も慣れてきやすくなります。)
・子どもとの時間が増える(仕事をしながらも子育てにもしっかり臨める)
・心身の負担が軽減する(職場にも大事にされている、必要とされていると感じますね。)
デメリット
・収入が減少する(どうしても出勤時間が少なくなる分減ってしまう)
・キャリアに影響が出ることも(長い目で見たらいっときのことですが、タイミングによるかも)
・同僚に気を使ってしまう場合あり、割り切る気持ちも必要(子供がいない方もいるので気になったり…)
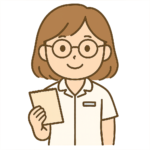
自分お使える制度は堂々と利用していきましょう。対応してもらえたら、職場や同僚にはしっかり感謝を伝えましょう。今は利用させていただいて、次は自分が支える側になればいいのです、持ちつ持たれつ!
④ ママ同士の協力・シフト調整
同じくらいのお子さんを持つスタッフ同士で協力することもあります。状況がわかっている分理解もあり、協力しやすいですね。お互いにお互いを理解しあっておける関係があるといいですね。
メリット
・希望のシフトを通しやすくなる(それぞれの家族の対応状況も加味しての協力も必要です)
・働くママ同士の連帯感が生まれる(子供たちも仲良くなって信頼も積み上がる)
・チームワークで支え合える安心感(みんなで育てる感覚があり、頼りになる存在)
デメリット
・相手の状況に左右される、風邪や感染症になった時の感染拡大の懸念もある(特に冬場は感染拡大のきっかけの一つに。関係悪化のきっかけになることもある)
・自分の希望通りにいかない日もある(協力体制がどちらかに偏ってしまうこともあり、不公平感も感じやすい)
・気を使いすぎてストレスになることも(他社サービスでない分、困ったことも言いづらい環境になる)
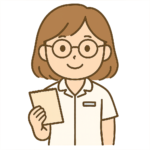
はじめは協力がしっかりできていたのに、次第に関係もなあなあになり、かえって関係悪化につながることもあるようです。親しき中にも礼儀あり!お互いに、感謝しつつ、手を差し伸べあえる関係であるといいですね。
まとめ:頼ることは、賢さであり、あたたかさ
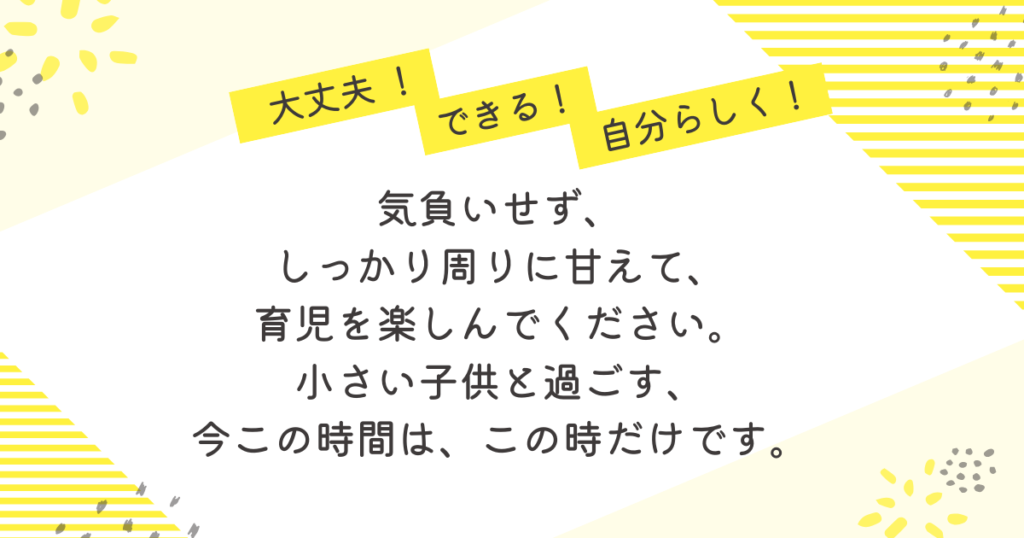
まとめです。さて、今日の記事はいかがだったでしょうか?何か一つでも参考になることがあれば嬉しいです。
- 私の経験:復帰の喜びと、葛藤の両方を感じた日々について
- 義理の祖父母へのお願い…私が気をつけたことについて
- 働くママが実践している対策と、そのメリット・デメリットについて
働きながら子育てをするというのは、決して簡単なことではありません。
完璧を求めすぎず、「自分にできること」と「誰かにお願いすること」をうまく組み合わせていくことが大切です。
頼ることは、弱さではなく、賢さです。そして、周囲との信頼関係を育むあたたかい選択でもあります。
お子さんとの時間を大切に、いつも笑っていられるママでありたいですね。気負いせず、しっかり周りに甘えて、育児を楽しんでください。小さい子供と過ごす、今この時間は、この時だけです。応援しています。
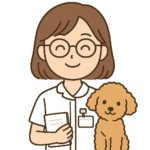
miu|助産師・2児の母・ブログ運営中
20年以上、病院で助産師として勤務。新人時代の不安や戸惑い、子育てと仕事の両立に悩みながらも、周りに支えられてここまできました。
このブログでは、助産師学生・看護学生、そして働くママたちが「今日もがんばったね」「ちゃんとやってるよ」と、自分を優しく認められるような言葉を届けています。
あなたがちょっとだけ元気になれる、そんな場所になりますように