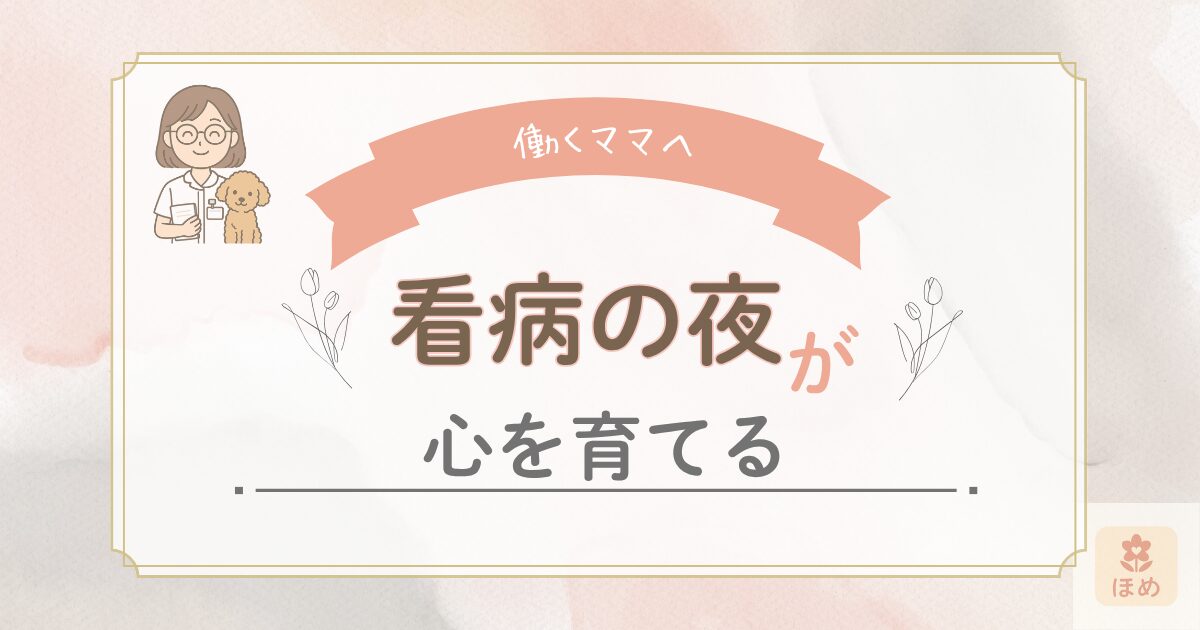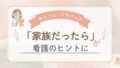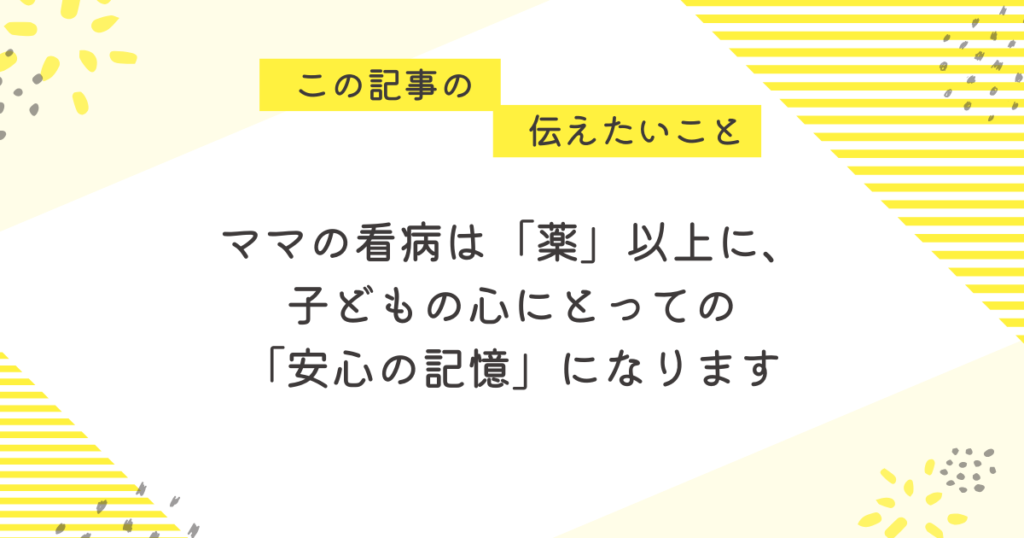
結論:どんなときも見守ってくれる存在がいる」という確信が、自己肯定感の基盤になります。
はじめに
こんにちは、miuです。5月になりましたね。
新しい生活に少し慣れてきたようで、まだ手探りな毎日。
産休明けの復帰をしたママさん、今のこの時期は、体も心もふらふらと揺れる日々ではないでしょうか。
少しずつ慣れてきたのに、保育園からの突然の呼び出しもありますね。
保育園からの突然の電話──「お熱が出ました」「お迎えをお願いします」
職場で言い出しにくい空気の中、まだ慣れない仕事を調整して、申し送りや記録を終えてから迎えに行く。焦る気持ちと、職場への申し訳なさが入り混じる時間ですね。
泣きじゃくる子を抱えて、眠れない夜を乗り越えなければなりません。帰宅してからも、やることは山積み。病院、診察、薬局、そしてぐずる子ども…。ご飯もあまり食べられず、薬も嫌がって飲まない。
夜になっても、泣き声で何度も目が覚めてしまう──
今日はそんな子どもの体調不良で、心身ともに疲れてしまうママに向けて、エールを送りたいと思います。
私も経験|子供の看病、いつまで続く?
私もそんな日々を何度も過ごしました。子どもが3歳くらいになるまでは、特に多かったです。
冬には、2人の子どもが時間差でインフルエンザ、胃腸炎…。看病がやっと終わったと思ったら、今度は私が感染して寝込んでしまうこともありました。「もう無理かも」と思いながら、それでも朝が来て、またお母さんを続ける。
さらに職場に迷惑をかけたかも…と落ち込む気持ちもありますよね。でも、「また誰かが困った時は私が助ける」と思っていれば大丈夫。「お大事にね」「無理しないでね」と声をかけ合うだけで、あたたかい気持ちが循環して、きっと自分にも返ってきます。
急な保育園呼び出しについてや頼ることの大切さについての記事は、他の記事でも紹介しています。そちらも参考にしてください。→夜勤と育児・保育園の両立に悩むママへ|頼ることで心が楽になる方法
この大変な時期は、ずっとは続かないから大丈夫です。子どもは少しずつ強くなり、風邪も減っていきます。この“何度も呼び出される時期”は、数年で落ち着いていくことが多いです。今だけのこの時間、
「あと少しだから、今日だけは寄り添おう」と思ってみてくださいね。
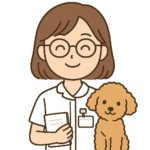
子供が小さい時は、本当にしょっちゅう保育園から連絡が来ますよね。私も復帰したての時は、早退することも気まずく、なんだか背中を丸めて帰っていた記憶があります。でも、もちつもたれつ、他の人が困ったときは自分が変わればいいのです。そして、この大変な時期は、いづれ落ち着いてきます。お子さんの個体差はありますが、3歳から6歳までくらいの間には頻度は落ち着いてくると思います。最中にいるママは終わりの見えない看病に感じますが、次第に回数も少なくなりますよ。
子どもが看病してくれているママに対して思っていること
子どもは発熱してつらいとき、ママがそばで看病してくれていること自体が大きな安心になります。年齢や言語能力によって表現は違っても、子どもはママの存在を全力で感じ取っています。以下にまとめてみました。
👶 まだ言葉にできない小さな子(乳幼児)
- 「ママがそばにいるだけで、安心する」
- 「苦しいけど、ママの声が聞こえると安心」
- 「ママの手、気持ちいい…」
- 「ママはいつも僕を守ってくれる」
🍼➡️ 体調が悪いときこそ、ママの匂いやぬくもり、声、目線など、五感を通して愛を受け取っています。
🧒 幼児〜小学校低学年くらい
- 「ママ、ありがとう」「ママ、大好き」
- 「ママ、すごいな…」
- 「こんなに優しくしてくれるママって、すごく特別」
- 「ママがいるから安心して眠れる」
🍀➡️ 病気のときに「甘えられる」体験は、子どもの心に深く残ります。
だからこそ「ママの優しさ=愛情」として、後の人生にも影響する安心感を育てます。
🧑 小学生〜思春期の子どもでも…
- 「うざいって思っても、やっぱりママがいてくれるのが一番落ち着く」
- 「ママって、何があっても味方でいてくれる」
- 「自分のことを一番に考えてくれてるってわかる」
- 「ママって、すごく強くて優しいな」
🌟➡️ 照れや反抗の裏には、「ちゃんと見てくれている」「愛されている」という確信があります。
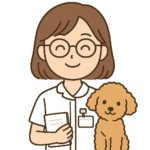
あなたも小さい時、家族が看病してくれた記憶はありませんか?ママが夜中に寝不足でも熱を測ったり、汗を拭いてくれたり、薬を飲ませたり、何度も起きて声をかけてくれたことは、子どもにとっては「世界で一番やさしい記憶」になります。ママの愛情、しっかり感じ取っていますよ。
愛情ある看病を受けた子どもの心理的影響
愛情ある看病を受けた子どもは、心理的に以下のような良い影響を受けることが研究で示されています。表にまとめました。
愛情ある看病が子どもに与える心理的な影響
| 効果 | 内容・説明 |
|---|---|
| ① 安心感と信頼感を育む | 「どんなときも見守ってくれる人がいる」という経験が、自己肯定感の土台になる。 |
| ② 安定した愛着(アタッチメント)の形成 | ボウルビィの愛着理論では、病気時に応答してくれる大人の存在が「安全基地」となり、精神的な安定に繋がる。 |
| ③ ストレス耐性(レジリエンス)が高まる | 不安な経験を「安心できる人と一緒に乗り越えた記憶」が、将来の困難への強さになる。 |
| ④ 共感性が育つ | 大切にされる経験を通して、人へのやさしさや思いやりが育まれる。 |
| ⑤ 病気や不安への過度な恐怖が減る | 「病気=怖いこと」ではなく、「大丈夫になれる」と学習し、安心して過ごせるようになる。 |
ママの看病は、子どもの心にこんなにも良い影響を与えています。
「そばにいてくれる安心」が、子どもの人生の土台になることをまとめました。
いかがですか?きっとあなたは、このような良い心理的影響を意識せずに、精一杯、お子さんの看病をおこなってきたのではないでしょうか?それがこんなにもお子さんの気持ちを支えていた行為だとは思いもよらなかったのではないでしょうか?お子さんの人生の基盤、絶対的安心感となっているのです。ママの存在はすごいですね!あなたの頑張りは、素晴らしいものです。
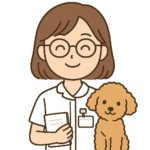
母の力は絶大ですね!そしてその母を一生懸命行っているあなたの行動は、もっと評価されるべきものです。子供の看病をしても、誰からも褒められることはないですものね。ぜひ私に褒めさせてください!
「あなたの看病は、人一人の人生の土台を作るような素晴らしいことです。それはただの看病ではありません。泣きじゃくるお子さんを、腕が痛くなっても抱きしめて、あなたの時間と睡眠を削り、見返りを求めず、ただ回復を願い尽くした大変なことです。あなたの愛情をたっぷりもらったお子さんは、生涯その記憶を忘れず、心の土台もしっかりとしたお子さんになるでしょう。あなたは、誰よりも優しくて、誰よりも強いお母さんです。本当にすごいです!」
参考文献:
- ボウルビィ, J.(1988)『愛着と喪失』誠信書房
- エリクソン, E.H.(1963)『幼児期と社会』誠信書房
- Werner, E. & Smith, R.(1982)“Vulnerable but Invincible” McGraw-Hill
- 日本小児心身医学会監修(2022)『子どもの心と体の理解と支援』日本評論社「ボウルビィの愛着理論(アタッチメント理論)とは?愛着行動を簡単に解説」
- 参考リンク:やさびと心理学 養育者との関係性を4段階に分けて整理し、理論のポイントや実験例(ストレンジ・シチュエーション法など)も丁寧に解説されています。
まとめ
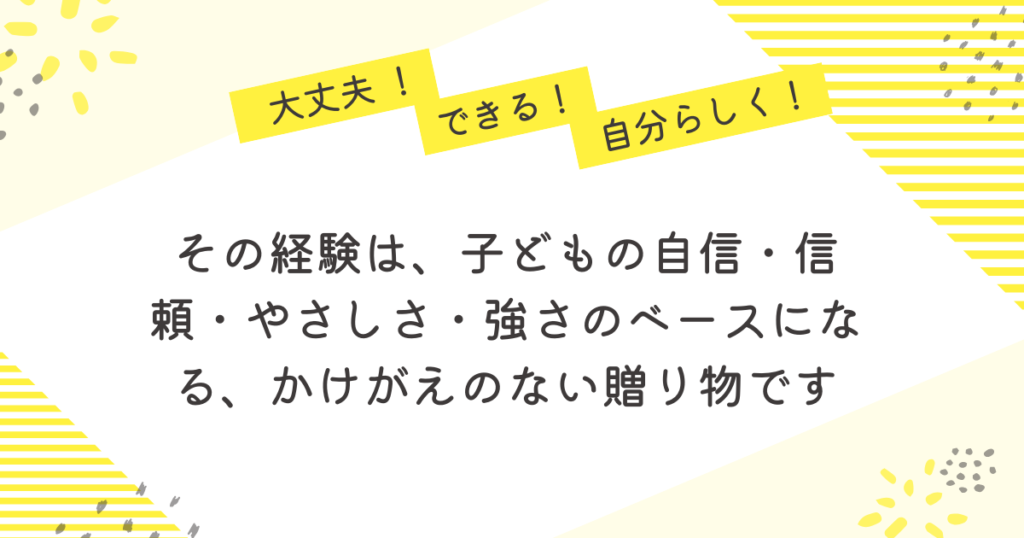
さて、今日の記事はいかがだったでしょうか?自分のしている「看病」にそんな効果があったなんてと思われた方、大変だけどやる意味があって支えになったなどと思われた方もいたのではないでしょうか?
「ママがそばにいてくれた」──そのぬくもり、ちゃんと伝わっています。泣いていた時、眠れない夜、熱がある日も、ママがそばにいてくれたことは、きっと子どもの心に残っています。あなたの愛情は、言葉よりもしっかり伝わっています。
ぐずる子どもにイライラしそうになっても、心配しながらお迎えに行ったあの日も、泣きながら薬を飲ませようとしたその手も、どれもすべて、愛情そのものです。「もう無理…」って思っても、それでもやめずに頑張っているその姿、本当に本当に、素晴らしいです。
胸を張って!応援しています。

miu|助産師・2児の母・ブログ運営中
20年以上、病院で助産師として勤務。新人時代の不安や戸惑い、子育てと仕事の両立に悩みながらも、周りに支えられてここまできました。
このブログでは、助産師学生・看護学生、そして働くママたちが「今日もがんばったね」「ちゃんとやってるよ」と、自分を優しく認められるような言葉を届けています。
あなたがちょっとだけ元気になれる、そんな場所になりますように。