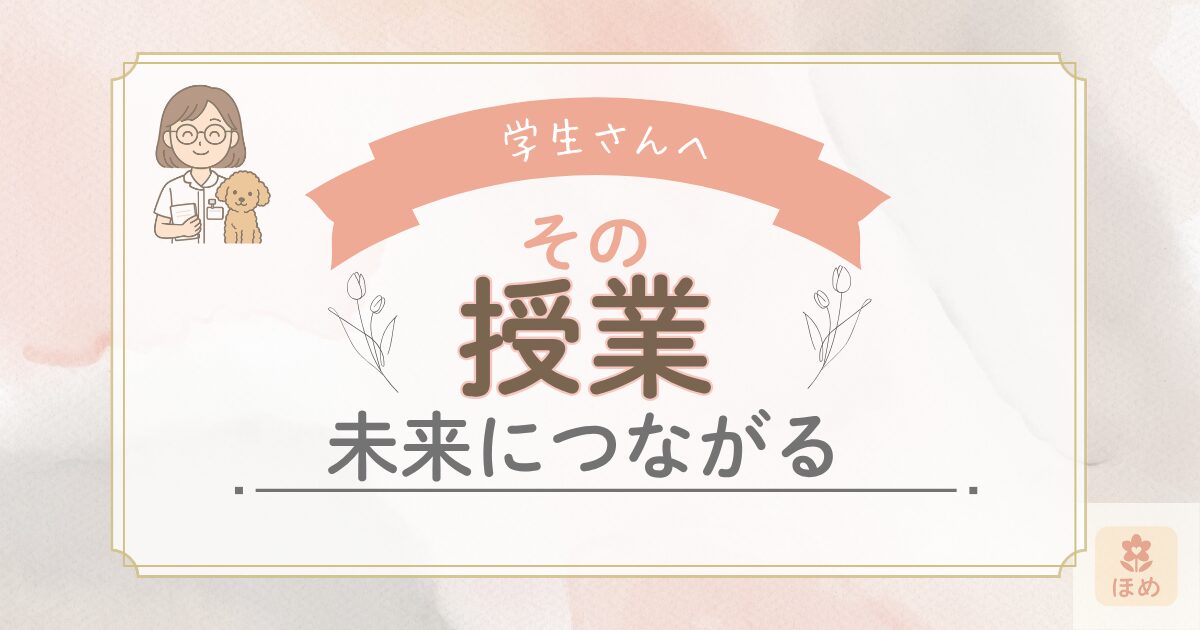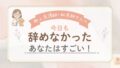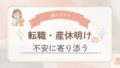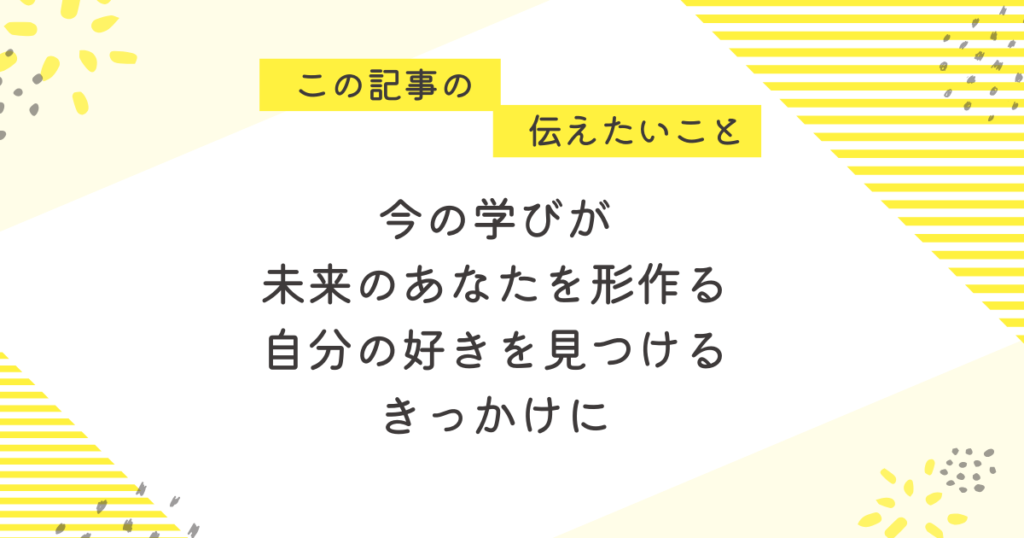
結論: 授業でいろんな分野を学ぶことは、「自分の好き・得意・やりたいこと」に気づくきっかけに。
はじめに
こんにちは、miuです。
新年度が始まり、看護学生さんや助産師学生さんは新しい授業がスタートしている頃ですね。
聞き慣れない言葉や、専門的すぎてピンとこない科目に戸惑っていませんか?
そして、授業の内容によっては、「これ、現場で本当に使うの?」「意味あるのかな…?」
そんなふうに思った内容があったことも多いかもしれません。
結論から言うと、意味はあります。今取り組んでいるその授業や学びは、実は“将来の自分”を知る大切なヒントでもあるんです。
今日は、なぜその授業が「意味はある」のかをお伝えしたいと思います。
看護学生が「意味がない」と感じやすい授業の場面
ではまず、看護学生はどのような時に授業に「意味がない」と感じるのでしょうか?以下に表にまとめてみました。自分に当てはまる部分はあるでしょうか?

この授業、あまり興味がない…。こんなこと覚えて、実践に役に立つのかわからない…。この学習するなら他の勉強したい…。
| 原因カテゴリ | 具体的な場面・理由 | 説明 |
|---|---|---|
| 実践との結びつきが弱い | 臨床での活用が見えない | 哲学・倫理・統計など、現場と結びつけて説明されない授業 |
| 学びの目的が不明確 | 何のために学ぶのかがわからない | 「将来の役に立つ」と言われても実感が湧かない |
| 暗記中心の内容 | 単なる用語や定義の丸暗記 | 活用の場面がなく「試験のためだけ」に感じる |
| 教員の伝え方が一方的 | 教科書の読み上げのみ、興味を引く工夫がない | 学生の関心を引く実例や現場の話がない |
| 関心・経験とのギャップ | 自分の興味外の分野(精神・小児など) | 「将来使わないかも」と思ってしまう |
| 忙しさ・ストレスの影響 | 実習や課題に追われて余裕がない | 「今やらなくてもいいのでは?」と後回し思考になる |
授業の内容は、その科目の得意、不得意、好き、嫌いに関わりますよね。とても大事なことです。今までの中学や高校の授業の経験からもわかるのではないでしょうか?
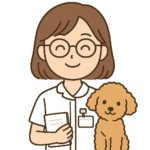
私も学生の頃は、専門的すぎる内容に、あまり興味を持てなかったり、意味があるのかなと思いながら学習した記憶があります。時間に追われることが多く、今これ必要ないなら、こっちの学習したいな…なんて思っていましたね。いづれこの知識が役にたつということをその時はまだ気づいていませんでした。
看護学生が「この授業、ためになった」と思う時の具体例
では逆に看護学生が、「この授業、ためになった」と感じる時はどんな時でしょうか?
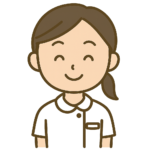
実際に現場に出たら、やっとこういうことかと実感した。臨床指導者さんに聞かれたことが、学習した内容で答えることができた。学校の先生が言っていたことは、本当だったんだ…。
| 実感の瞬間 | 具体的な場面・理由 | 説明 |
|---|---|---|
| 実習や現場で知識が活きたとき | 習ったフィジカルアセスメントが実際に役立った | 「授業の内容がそのまま使えた!」という体験が自信に |
| 国家試験対策で役立ったとき | 「先生の解説が試験に出た」 | 試験に直結する知識だと、納得感が増す |
| 実際の患者のエピソードと結びついたとき | 授業で紹介された症例に似た患者さんを担当 | 知識が“生きた情報”として記憶に残る |
| 教員が熱意をもって教えてくれたとき | 教員の実体験・エピソードが心に残った | 感情を動かされた授業は記憶にも深く残る |
| グループワークでの学びが深かったとき | 他の学生の視点から気づきがあった | 自分だけでは得られなかった視点に出会える時間に |
| 自分の目指す看護像と重なったとき | 「患者さんに寄り添うことの大切さ」が響いた | 自分の価値観とリンクすると強く残る |
| 現場で「よく知ってるね!」と褒められたとき | 看護師から知識を褒められて嬉しかった |
「意味ないかも…」と思っていた学びが、「あの瞬間、つながった」と感じたエピソード一覧です。
いくつか当てはまる部分はありましたでしょうか?学生は「これって何のために学んでいるのか?」について納得できると、授業を前向きに捉えやすいです。学びと実感の一致が多くあった時、特に、臨床や実習、将来の自分像と結びついたときに強くそう感じるようです。
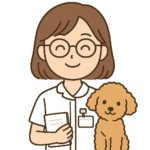
学習との関連がわかると、腑に落ちてスッキリ知識として吸収できますよね。なんで必要なのか、考えて答えのない学習もありますが、それもいづれ自分の判断につながるとわかっていれば、「意味」を感じることができますね。
看護・助産の世界は、思っている以上に広い
ではなぜ、意味がないように感じる学習をしていくのでしょうか?さまざまな理由があります。
- 知識を深掘りする
- その分野の「概要」を知れる
- 「自分が好きかどうか」に気づける
- 自分が実は研究に向いているかもしれないと気づける。
こうした気づきは、将来自分がどんな道に進みたいかを考えるうえで、とても大切な材料になります。「看護師」「助産師」と一言でいっても、働く場所やスタイルはさまざまです。
看護師なら…
- 総合病院でたくさんの診療科を経験したい人
- 高齢者の介護や看取りにやりがいを感じる人
- 小児科やNICUで働きたい人
- 訪問看護で一人ひとりと丁寧に関わりたい人
- 専門的な診療科(例えば手術室、透析など)を極めたい人
助産師なら…
- 総合病院で分娩介助を中心に働きたい人
- 助産院で“その人らしい出産”を支えたい人
- 乳房ケアや母乳育児の支援を専門にしたい人
- 教育や研究の道に進みたい人
今の学びが「自分の好き」を見つけるカギになる
授業でいろんな分野を学ぶことは、「自分の好き・得意・やりたいこと」に気づくきっかけでもあります。
今はピンとこなくても、「あの授業で学んだ〇〇、面白かったな」「もう少し勉強してみたいな」と思えたことは、将来の方向性につながります。
目の前の勉強に意味があるかどうかを決めるのは、これからのあなた自身です。
だからこそ、“未来の自分”のために、今の学びを大切にしてほしいのです。
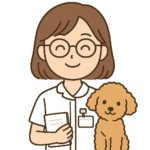
私も助産師を目指しきっかけは、母性看護の実習でした。助産院へ行き、実際の助産ケアを目の当たりにしました。産後の育児に悩む、落ち込んでいたお母さんが、パアッと顔が明るくなって帰っていく姿を見て、「助産師」ってすごい!と強い影響を受けたことがきっかけでした。それまでは自分が助産師になりたいなんて、考えてもなかったのです。あの時の自分があるから、今の自分がありますものね。
後で意味がわかる「時間差の学び」
看護学生さんが、意味がないと思っていたけれど、実は役に立ったと感じる瞬間について表にまとめました。
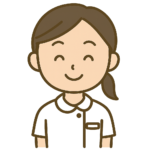
学校で学習した時は、意味がわからなかったけれど、実習に来て患者さんを目の前にして、全体像を見たら、とても大切な重要なことだったと気づいた。
| 授業の時はこう思った… | でも、実はこんな風に役立った! | 気づきのポイント |
|---|---|---|
| 「統計学って看護に関係ある?」 | 卒論でエビデンスの意味がわかった/医療データの見方が理解できた | 専門職としての視点が持てた瞬間 |
| 「哲学・倫理の授業、抽象的すぎる…」 | 患者さんの価値観に寄り添う姿勢が求められた場面で思い出した | 目の前の人を“人”としてみる力 |
| 「看護過程って面倒くさいだけ」 | 実習で患者さんの全体像をつかむのに役立った | アセスメントの土台になることを実感 |
| 「座学ばっかりで眠くなる…」 | 実習中、急変対応の知識が頭に残っていて冷静に行動できた | 知識が“反射的”に出てきた経験 |
| 「精神看護、よくわからない」 | 実習で精神的に不安定な患者さんと接したとき、講義内容が活きた | コミュニケーションの深さに気づいた |
| 「興味ない分野だから流してた」 | 配属先がその分野だった/就職面接で役に立った | 学びは“引き出し”として残るという実感 |
| 「全然ピンとこない」 | 国家試験対策で「あれ、これ授業でやったな」と思い出した | 無意識に残っていた知識の再発見 |
「授業の意味がわからない」が「役に立った」に変わった瞬間|看護学生の気づき一覧
この表からわかることは、「今はわからないけど、あとで意味がわかる」という時間差の学びです。
看護学生が「意味ないと思ってたけど、これ…実はすごく役立ってる!」と気づくのは、「現実の場面で知識や経験が結びついた時」や、「自分の成長を実感した時」です。すぐに実感できるものではない、時間差で意味がわかってくるものなのです。「わからないとき=無意味」ではなく、「あとで効いてくる知識や気づき」こそ、学びの“種”となります。
同じように、実習に出る前に学んだ略語がわからないことに対する記事は他の記事でも紹介しています。こちらも参考にしてください。→略語がわからない…でも意味がわかれば怖くない|看護学生へ
おわりに
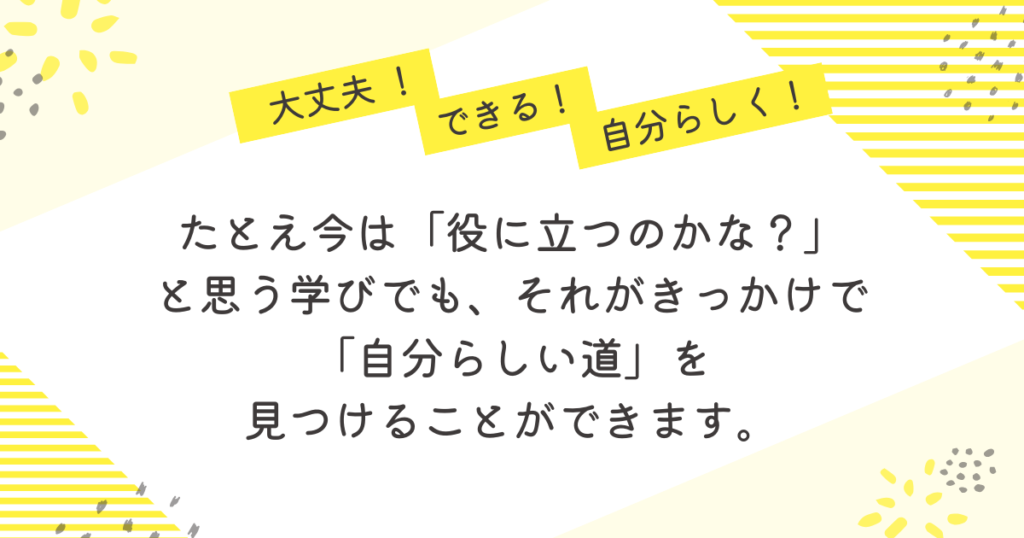
さて、今日の記事はいかがだったでしょうか?
たとえ今は「役に立つのかな?」と思う学びでも、それがきっかけで「自分らしい道」を見つけることがあります。ひとつひとつの授業や実習が、あなたの未来にちゃんとつながっています。
目の前の授業、課題をこなすこと、全て自分に返ってきます。そして自分らしい素敵な道を見つけてくださいね。今日の学びも、未来のあなたの力になりますように。
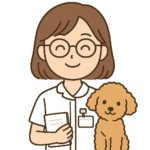
miu|助産師・2児の母・ブログ運営中
20年以上、病院で助産師として勤務。新人時代の不安や戸惑い、子育てと仕事の両立に悩みながらも、周りに支えられてここまできました。
このブログでは、助産師学生・看護学生、そして働くママたちが「今日もがんばったね」「ちゃんとやってるよ」と、自分を優しく認められるような言葉を届けています。
あなたがちょっとだけ元気になれる、そんな場所になりますように。