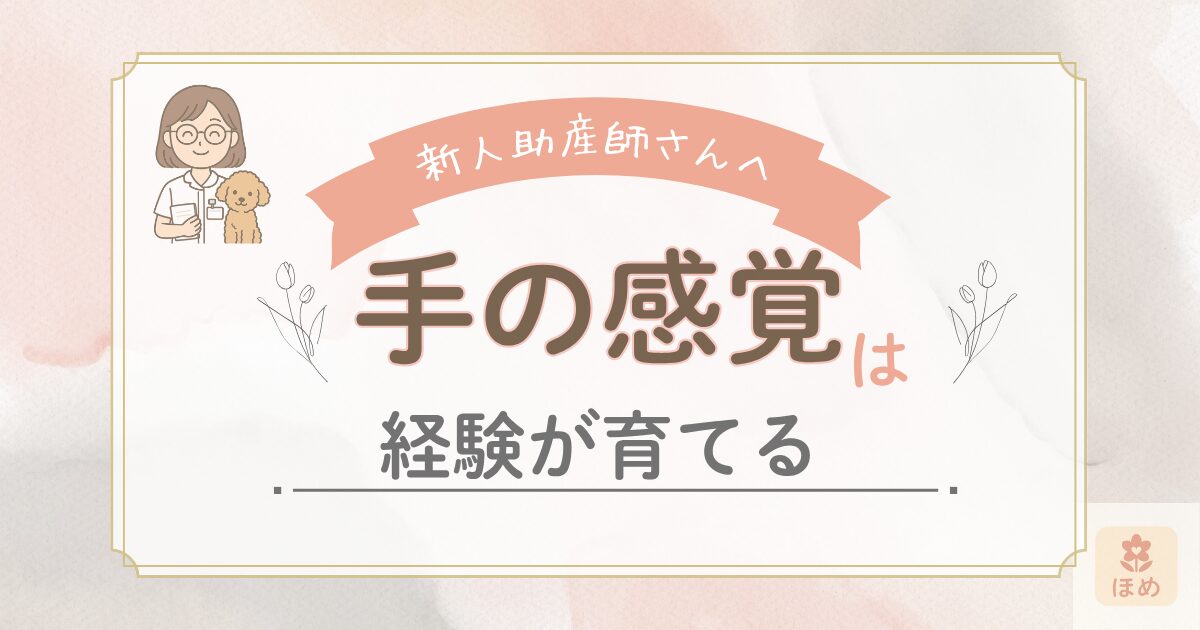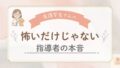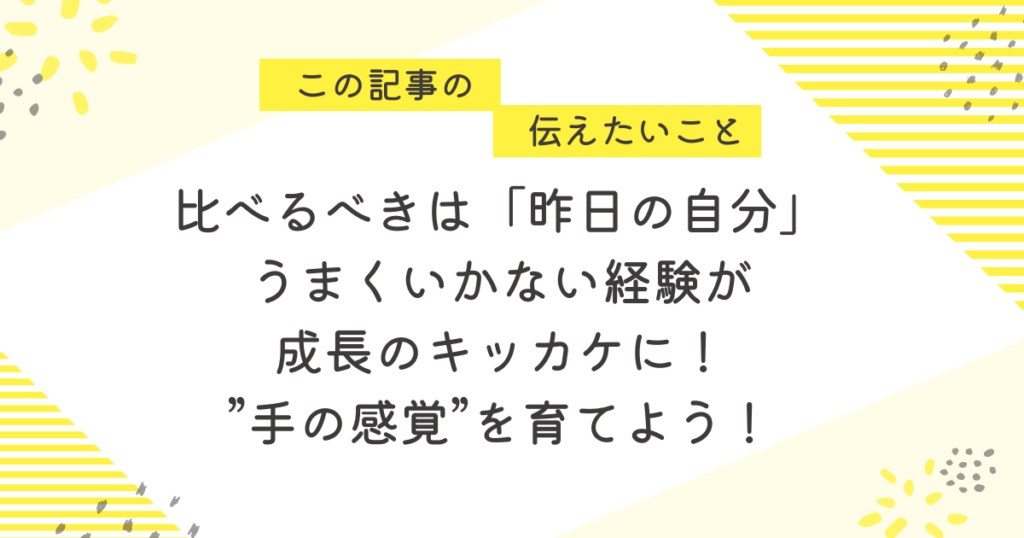
結論: 失敗がなければ成功なし!うまくいかない経験が成長のもと!”手の感覚”を育てよう!
はじめに|新人助産師さんの分娩介助ができないという悩み
こんにちは、miuです。
新人助産師として歩み始めたこの春、みなさんはもう何例くらいの分娩介助を経験されましたか?分娩介助がで思うように出来なかったり、まだコツも掴めずにうまくいかないと感じている悩みを持っている人も多いのではないでしょうか?
学生時代に10例ほど分娩介助を行い、先輩や臨床指導者さんの「手の感覚」を頼りに、何とか介助をこなした日々。やっとやり方に慣れてきたと思った頃に実習が終わり、国家試験に集中し、しばらく分娩介助から離れたまま、臨床に出て“仕事として”分娩に携わるようになったという方も多いのではないでしょうか。
今日はそんな新人助産師さんへ向けて、分娩介助がうまくできるようになる意識の仕方、ヒントについてお話しさせていただきます。私の思いや経験も含めて書きますので、何か少しでも参考になれば嬉しいです。
「もう学生じゃない」からこそ、プレッシャーを感じていませんか?
新人助産師さんは臨床に出てから、学生の時とは違う環境になります。あなたは努力の末、国家試験で合格し、助産師の免許をもった”プロ”になりました。患者さんからも”プロ”という目で見られ、頼りにされる存在になりました。そして現場でも、先輩スタッフからも”同僚”という立場となり、ある程度「できているもの」として見られるようになりましたよね。嬉しい反面、不安もつきまとうと思います。
学生時代とは違い、先輩からの指導も、少しずつ“自分の判断”が求められてきます。学生のころのように手を添えて、丁寧に解説しながら毎回教えてもらえるわけではありません。いざ業務に入れば、自分の分娩介助を一からサポートしてもらえる機会はなくなり、自分で課題を見つけて、実行して、振り返って…という繰り返しの毎日になります。その状況も慣れるまでは不安で、自信がなくて、プレッシャーですよね。
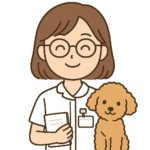
新人時代、私もプリセプターの先輩がいなくなると不安で、慣れるにはしばらく時間がかかったことを覚えています。そして現在、もう私の分娩介助を評価してくれる人はいません。でも唯一評価してくれる人がいます。それは”自分”です。そして、現在まで数千件の分娩介助を行なっていますが、毎回必ず振り返りをしています。今もなお、精進し続けており、”きっと終わりはないのかな?”と思っています。
私自身、これまで数千人の方の分娩に関わり、数千件の分娩介助をしてきました。それでも、「今だに課題はある」とはっきりと言えます。
- 分娩進行の助産診断(それぞれの状況ごとに診断し直して、分娩予測と対応を検討)
- 呼吸のリード(産婦さんに合わせた声かけ、産む力を引き出せる関わり)
- 会陰保護の手の感覚(赤ちゃんの出たいペースと会陰の伸展に合わせたコントロール)
- 分娩のスピード感の調整(産婦さんのペース、赤ちゃんの状態に合わせた最良の調整)
この内容はほんの一部ですが、たくさんの状況を想定して、安全に赤ちゃんとお母さんに合わせた援助を行います。
これらは毎回変化があり、同じお産は一つとしてありません。 蓄積された経験をもとに助産診断を行い、「これがベスト」と思う介助を選び、その結果がどうだったかを、毎回必ず振り返っています。
予測どおりにうまくいったこともあれば、想定外の結果になり反省することももちろんあります。でもそれこそが、分娩介助の“経験の糧”でもあるんです。助産診断をして予測して関わりますが、その”答え合わせ”は、終わった後に振り返るしかありません。ひとつひとつのケースに合わせた”答え”を積み上げ、”自分の軸”にしていくしかないのです。
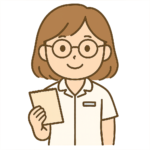
数千件の分娩介助を行なってきましたが、分娩進行の判断は全て分娩の3要素(産道・胎児娩出物・娩出力)に通じていると言えると実感しています。主となる助産診断はこの3要素全てに対しての評価となります。分娩介助は赤ちゃんを取り上げて、会陰を保護するだけではありません。さまざまなケースに対して、経験を積み、振り返り、そして自分の助産診断基準を確立できると良いでしょう。
私の失敗経験と”手の感覚”を育てること
私も先輩の評価を受けられなくなってから、しばらくは自分の課題をうまく見つけられないことがありました。数をこなしていくうちに、慣れてはいきます。しかし、次の課題につながるかというと、課題が明確になっていなかったと思います。なぜ、課題を明確に持てなかったと感じたか…。
それは同じような失敗をしていたからです。
もちろん気をつけていましたが、自分でコントロールしきれずに思いの他、傷ができてしまったり…。なんか同じようなこと、前にもあったかも…。と、ハッとした記憶があります。
自分はすでにその経験をしていたのです。それにもかかわらず、今回の分娩介助でその失敗を活かせなかった。自分の課題が明確になっていなかったと気づいた瞬間でした。産婦さんは、産後に感謝の言葉を私にかけてくださりましたが、私の心は”産婦さんに申し訳ないことをしてしまった…”と、反省の嵐でした。
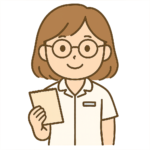
自分の意識の低さが、直接産婦さんへ影響が出るのが私たちの判断です。私の失敗の経験は、今ではそれも含めて糧となり、”絶対に同じような失敗は繰り返さない!そのためには…”と必ず振り返り、考えるきっかけとなりました。新人助産師の皆さんにも、私のような苦い経験をなるべくしないようにしていただけるといいなと思います。
分娩介助に「課題意識」を持つことが成長につながる
臨床の現場に出てからは、自分で予測し、判断し、実行し、結果を振り返り、次回への課題を明確に持つこと。この繰り返しをしていきます。それがどんな効果があるかを以下にまとめました。
2022年に岡山県立大学保健福祉学部の紀要に掲載された研究によると、看護学生の「自己調整学習力(自信をもって学習計画→実行→振り返りを行う力)」と「自己効力感(自分ならできるという感覚)」には有意な相関が認められています。つまり、自分で目標を設定し、意図的に学びをコントロールできる学生ほど、技術や実習に対する自信を強く持つ傾向があるとされています。
【参考】岡山県立大学 保健福祉学部紀要(2022年):「看護学生の自己調整学習と自己効力感の関連について」 ※現在、大学公式サイト内で該当紀要が公開されていない場合があります。
また、分娩介助に「課題意識」を持つことが成長につながるという研究もあります。
J‑STAGEに掲載された研究では、臨床指導者が助産師学生に対して「課題の設定→判断・実施→振り返り」を促す教育が行われ、その結果学生の自己効力感(“自分にもできる”という自信)が高まったことが報告されています。
👉 分娩介助実習における助産師学生の自己効力感を高めるための臨床指導者の教育の実践
(永井紅音・荒木奈緒/J-STAGE)PDF)
これらの研究からも、課題をもつことの重要性と効果はわかりますね。
課題の意識を持つか持たないかで、時が経ったときの技術の差は自然と開いてしまうかもしれません。しかし、分娩介助の技術の取得は、誰かと正しく比べることはできないんです。同じ妊婦さんの分娩を、二人の助産師が介助することはありませんから。誰かの手の感覚を、自分が感じることはできないですよね。
練習するたびに自分の手技となっていくことの記事はこちらでも紹介しています。参考にしてみてください。→実技で緊張する学生さんへ|緊張を乗り越える考え方
つまり、誰かと比べるよりも大切なのは「昨日の自分」と「今日の自分」。自分自身を比べることしかできないのです。あなたが目指す技術の習得は、自分自身でしか評価できないものなのです。
先輩の分娩の外回りに入りながら、見ること、聞くことで技術を身につけることはできます。 でも、同じ結果を目指すとしても、先輩と同じ感覚で介助できるわけではありません。
あなた自身の手の感覚。これを育てていくしかないのです。ぜひ、自分の手を育ててください。そして10年後、助産師を続けてきたあなたの分娩介助は、その素晴らしい「自分の手の感覚」で、自信を持って行うものとなっていることでしょう。
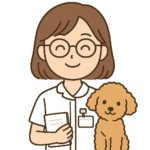
自分の”手”が、いつか”ゴットハンド”になれるように、まずはひとつひとつの分娩に真剣に向き合いましょう。課題を明確に持たないまま、ただ分娩介助に望んでも、次につながる課題は持てないでしょう。何より、人生で数回しか経験をしない貴重なお産をする産婦さんへ、プロとして関わる姿勢としてとても重要で大切なことです。
まとめ
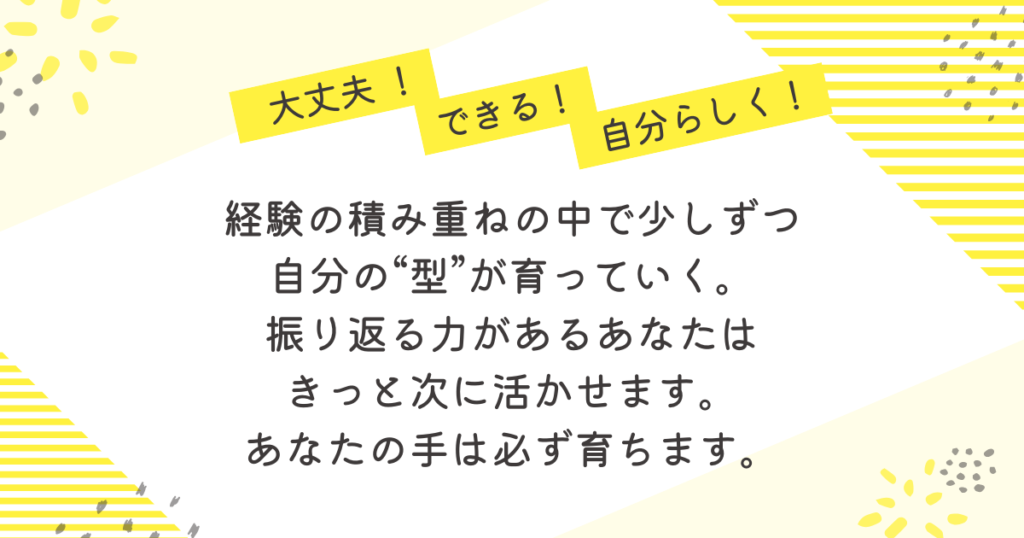
さて、今日の記事はどうだったでしょうか?まとめです。
- はじめに|新人助産師さんの分娩介助ができないという悩み
- 「もう学生じゃない」からこそ、プレッシャーを感じていませんか?
- 私の失敗経験と”手の感覚”を育てること
新人助産師さんは、まだまだ始まったばかり。自分の評価は当然まだできません。それでもひとつひとつの分娩に真摯に向き合い、経験をすることはできます。そして比べるのは、昨日の自分と今日の自分。この意識を持って介助に臨むことができれば、あなたはきっと頼れる、安心感のある素晴らしい技術を持った助産師に成長していきます。
できないことは恥ずかしいことではなく、成長するためのチャンスです。
焦らなくて大丈夫。あなたのペースで、あなたの手を、あなたの助産師としての形を育てていってください。心から、応援しています。
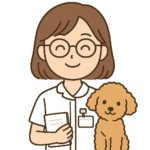
miu|助産師・2児の母・ブログ運営中
20年以上、病院で助産師として勤務。新人時代の不安や戸惑い、子育てと仕事の両立に悩みながらも、周りに支えられてここまできました。
このブログでは、助産師学生・看護学生、そして働くママたちが「今日もがんばったね」「ちゃんとやってるよ」と、自分を優しく認められるような言葉を届けています。
あなたがちょっとだけ元気になれる、そんな場所になりますように。